2005年度は、天候が安定し、栄養価の高い牧草が育ち、牛の健康状態もよかったことから、生産量が爆発的にのびたため、製造量と比較して消費量が減少していることも、その差が大きくなってしまったのではないかと推測されています。
このような状況のなかで、酪農家は、子牛に飲ませたり乳の出をとめるなどで減産をしているようですが、生乳は長期保存がきかないため、余っても肥料や焼却処分しているのが現状です。
JA北海道中央会などで、2006年度から3%、約11万トンを減産する予定のようですが、酪農家の約9割は、減産計画に難色を示し、減産量は目標の3分の1に止まる見通しのようです。
※ 参考 『朝日新聞』平成18年4月7日(朝刊)
『読売新聞』平成18年3月25日(夕刊)、平成18年5月12日(朝刊)
地 産 地 消 を す す め よ う
もっと牛乳・乳製品をたべよう
1. 牛乳をとりまく現状について
| 飲用牛乳は、全国的に需要が減退しており、これを反映して製造量は95年から毎年1~2%減産傾向が続いています。 飲料の嗜好が“すっきり”した飲み口を求めるようになったことや健康志向から、お茶やスポーツ飲料、豆乳などの消費量は増加しているようです。 また、若者の朝食抜きの傾向や少子化による学校給食での消費量の減少も影響が大きいと推測されています。 (社)日本酪農乳業協会の『2005 牛乳・乳製品の消費動向に関する調査[要約版]』によると、牛乳を「飲む量が減った」と答えた人は16.3%で、「増えた」と答えた人の9.5%を上回っていました。また、「普段よく飲む飲み物」についてみると、2002年と2005年を比較した場合、「牛乳」は3.9ポイント減少していますが、「豆乳」は8.3ポイント、「野菜ジュース」は1.4ポイント増加しており、「ドリンクヨーグルト」も3.2ポイント増加しているものの、「コーヒー」や「無糖のお茶飲料」の伸びが大きく、そのほかにも「スポーツ飲料」のような牛乳以外の他の飲料の消費機会が増加していることがわかります。 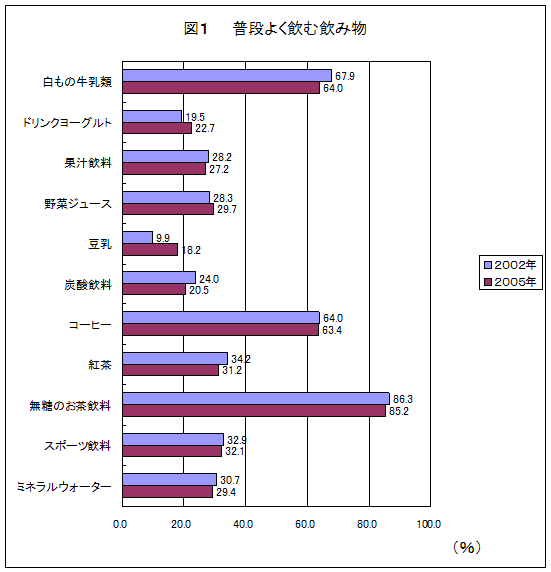
|
2005年の一人あたりの平均飲用量をみてみましょう。
全体では2004年とあまり変わりませんが、男性の20代では減少傾向が続いているようです。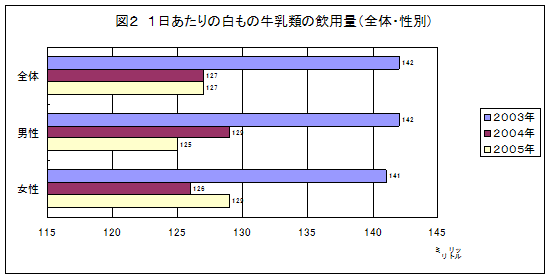
|
| また、一世帯(二人以上)あたりの牛乳の年間消費量をみてみると、北海道における年間消費量は、平成16年は89.16リットルで全国平均の102.32リットルを下回り、沖縄についで低い消費量になっています。 年間89.16リットルというのを、一日平均でみると(1日=365日とした場合)、一世帯で約244ミリリットルしか消費していない計算になります。 これは、200ミリリットルのパック入り牛乳で考えると、1個と5分の1程度の量にしかならないのです。 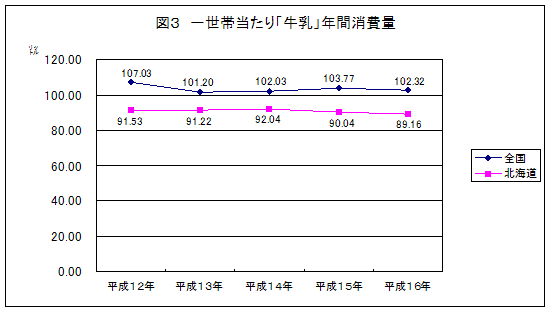
|
2. 牛乳・乳製品のチカラは?
牛乳や乳製品は、良質の栄養分を豊富に含んでいる食品です。
代表的な栄養素について、みてみましょう。
代表的な栄養素について、みてみましょう。
| ○ カルシウム |
| 牛乳自身にカルシウムの含有量が多いだけでなく、食事全体のカルシウム吸収を高めます。献立に乳製品をプラスするだけで、カルシウム摂取量がぐんとよくなります。 |
| ○ たんぱく質 |
| 大豆などの植物性たんぱく質に比べて、牛乳・乳製品は効率よく消化吸収されます。調理しなくても、そのまま飲んだり食べたりでき、手軽にたんぱく質を摂ることができる食品です。 |
| ○ ビタミン |
| 牛乳・乳製品はビタミンも豊富です。 たとえば、牛乳のビタミンB2は、コップ1杯で成人女性の一日の推奨量の約4分の1が摂取できるのです。水溶性ビタミンは、調理などによって栄養分が損失しますが、牛乳・乳製品は調理なしでも手軽に摂ることができるので、無駄がない理想的な食品だといえます。 |
| ○ コレステロール |
| 動物性食品はコレステロールが高いという先入観があるようですが、一食あたりに食べる量で、コレステロール値をみると、牛乳・乳製品はとても低いのです。 |
牛乳・乳製品の栄養については、下記のHPでも詳細をみることができます。
(社)日本酪農乳業協会の季刊誌『ほわいと』―ミルク解体新書―のページにリンクしています。
3. もっと牛乳・乳製品を食べよう
現状のままでは、生乳は、また余ってしまって廃棄せざるを得ないことになってしまうと予想されるます。
では、私たちは、何をしていけばよいのでしょう?
ひとりひとり、より多くの消費者が、良質な栄養素を含む牛乳・乳製品を普段から、今よりも多く食べたいものです。
“牛乳・乳製品を1日3回、、または3種類(牛乳、チーズ、ヨーグルトなど)摂りましょう”という、「3-A-Day」(スリー・アー・ディ)という取り組みもあります。
では、私たちは、何をしていけばよいのでしょう?
ひとりひとり、より多くの消費者が、良質な栄養素を含む牛乳・乳製品を普段から、今よりも多く食べたいものです。
“牛乳・乳製品を1日3回、、または3種類(牛乳、チーズ、ヨーグルトなど)摂りましょう”という、「3-A-Day」(スリー・アー・ディ)という取り組みもあります。
| ○ 「3-A-Day」とは? |
| これまでの食事に、牛乳やヨーグルト、チーズなどをちょっと加える。 たったこれだけのことで、これまで不足がちだったいろいろな栄養素を少ないエネルギーで補うことができるのです。 ルールは簡単。牛乳。・ヨーグルト・チーズの中から1日3回、または3品、食生活に取り入れるだけ。 難しく考える必要はありません。 たとえば、コップ一杯の牛乳を飲む、サンドイッチにチーズをはさむ、デザートにヨーグルトを食べる。 とにかく一品でも加えれば、それだけで充分効果的です。 毎日3回、または3品、気軽な新習慣。 ちょっと続けてみてください。 |
そのままでも、気軽に摂れるし、調理してもおいしく食べられるのが、牛乳・乳製品。
『太るのでは?』、『コレスロールが高いのでは?』などというのは、誤解のようです。もう一度、牛乳・乳製品のチカラを確認して、いつもの食事に牛乳・乳製品を加えてみませんか?
北海道は、牛乳・乳製品の生産地です。
地産地消の一環としても、北海道の牛乳・乳背品を食べるようにしたいものです。
4. リンクについて
牛乳・乳製品に関する栄養などの情報、レシピなどをみることができるHPにリンクしています。
豊富な情報を活用しましょう。
○ホクレン農業協同組合連合会 『ほっかいどう ミルクネット』
○社団法人 日本酪農乳業協会 『J - milk』
豊富な情報を活用しましょう。
【連絡先担当】 一般社団法人 北海道消費者協会 組織活性化グループ
TEL 011-221-4217 FAX 011-221-4219
TEL 011-221-4217 FAX 011-221-4219













